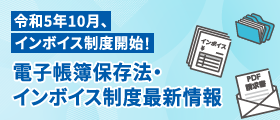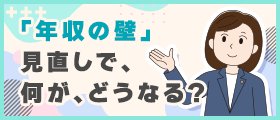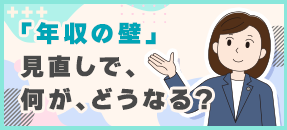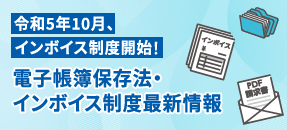知識と知恵は企業の力
Up Down方式 新・経営分析



経営トップの皆さんへ
投資家の皆さんへ
経営を学習中の皆さんへ
”率”を構成する
二つの項目( Item)の
増減(Up Down)を見ると
経営・景気・経済が分かる
目からウロコの、かつ
コロンブスの卵的
新らしい経営分析です。
ー Up Down方式分析の視点 ー
A経営を、「日本の景気判断」に直結する「栄枯盛衰の視点」で分析する。
B算式「売上-コスト=利益」ではなく、始まりも終わりもない「円周・循環運動」で考える。
C他社比較の「”率”分析」から自社動向を知る「増減分析」へ転換する。
Dその上で、増減分析を「成長動線・停滞動線・衰退動線」で表現し、さらに、点数評価する。
E経営の未来予測を「過去の動向」でする。
F経営改善の一丁目一番地は経営を「停滞動線」「衰退動線」を「成長動線」へ転換すること
一) 他社比較分析・”率”分析への疑問
アメリカ発祥の経営分析は、資金を貸すに値する企業か、投資するに値する企業か、そのための「他社比較評価」が中心となっています。百社百様、業種も形態も規模も違う会社の比較分析にはどうしても「率や割合」による分析が必要だったのかもしれません。その流れを汲み、現在の経営分析は、ほとんどが「率や割合」分析なのです。
ポピュラーな分析指標のうち収益性分析・安全性分析・ 生産性分析に所属する約18前後の指標は、分子分母とも増加しても減少しても「良くなったり、悪くなったり」します。つまり成長・衰退の判断材料にはなりません。 成長性分析の4前後の指標は、前年比較での「一項目」での成長・衰退は分かりますが、売上は成長している、利益は衰退しているということがおきます。4指標が全部成長してはじめて成長と言えるのです。詳しく主張できますが、「栄枯盛衰分析」には、従来の指標は向かないとだけ述べておきます。
二)計算式の視点から、円運動・循環運動の視点へ
計算式「売上-コスト=利益」は、出発点が「売上」で終着点が「利益」のように見えます。そこから売上を増やしコストを減らせば利益が出る、その繰り返しで企業は安泰だという立場に陥りやすい。
ところが、経営や経済は「コスト→売上→利益→コスト→売上→・・・・」という円・循環で考えると、いずれも出発点、いずれも目標・終着点となります。円運動は時計回りでも、反時計回りでも成立します。
そして、経営とは円の拡大「繁栄(成長)と継続」が重要と考えるようになります。
よく論ぜられる「利益中心主義」や「小さい会社論」や「無借金主義」は、経営の本論ではなく、やむをえない緊急策ということに気づきます。三つの同時成長(Ups)・円の拡大を”良”とするという確信を持つことが出来ます。
三)経営はなぜ栄枯盛衰するのか
資本主義経済は「自由な需要と供給運動」を通して、「適切な需要と供給」を実現します。計画経済ではないのです。つまり、言い方を変えれば企業の浮き沈みを通じて適切な「経済状況」を完成させるのです。理由①
次に、その中で企業間の生き残りをかけた競争が繰り広げられます。理由②
したがって、頻繁に企業は栄枯盛衰を繰り広げます。その時々の個々の企業の栄枯盛衰を知る必要があります。
四)栄枯盛衰の「成長動線」と「点数表現」の発見
経営の分析結果に点数を付けるために、成長動線・停滞動線・衰退動線を図式で表現することとしました。この動線の図式はここに紹介してあります。
この動線評価こそ「Up Down方式経営分析」の新しい視点です。難しいことは何も無く、しかも重要な図式となります。
過去は「ただの過去」ではなく現在や未来に繋がる「動向」を表現して、経営分析に一石を投じました。さらには経営の通信簿として「点数化」に成功したのです。
五)決算評価書の役割とは
ここで、決算報告書と決算評価書の本質的違いについて述べておかなくてはなりません。
決算報告書→「利益の”計算機”」
利益は日々の取引では表面には出てきません。決算書のみが複式簿記による記帳を元に「利益」を我々に知らしめてくれます。したがって決算書の本質は「利益の計算機」と言っても間違いではありません。決算書の使命は、「利益の計算」と、その報告なのです。
決算評価書→「経営の”通信簿”」
決算評価書は新しい役割を果たします。企業の直近の景気や業績、そして動向を動線と点数で評価しますので、まさに「通信簿」に値するものです。
さらに動向の「外部要因」「社内要因」「経理要因」をも検討します。
さらに動向という事実による「明日の予想と明日の計画(経営計画)の骨格」を検討することが出来ます。
経営計画書→「経営の”成長企画書”」
経営改善は「停滞動線や衰退動線」から「成長動線」への変更、成長への挑戦と位置付けられるでしょう。
六)利益は表面には出てこない
「利益の性質」を知れば「経営の本質」が分かります。
例えば建設業における「見積書」に利益と言う項目はありません。また商品売買の現場には売値と消費税しかありません。しかし「儲け」という概念は売手の頭の中に願望とともに存在します。売値の「自由性」「秘密性」と言うのが資本主義経済の本質でもあります。
つまり「利益(儲け)」は「売上」に隠れて存在します。表舞台には登場しないのです。「利益」が秘密にされていることにより、取引はスムーズに行われ、資本主義経済は発展してきたと言ってもよいでしょう。
利益を唯一教えてくれる「決算書」は経営分析の根本的資料となるのです。
七)Up Down方式経営分析で経営の最重要課題を知る
「直前の動向」というものが明日を占うものとなり、「経営者と経理と営業と製造現場など」の四者にとっての共通の言語となります。
特に経営の統括者である経営者の経営コントロールの必需品になるべきものです。
新・経営分析は、経営の異常を瞬時に示唆してくれる「体温計」「血圧計」のようなものでもあります。
新・経営分析は直ちに対策を求めてきます。根本的・大局的課題が認識され、多くの取り組むべき、あるいは改善すべき行動に我々を導くことになります。
八)経営計画の真の目的とは
Up Down方式経営観は「利益の増加」を目指すものです。「利益の発生」(黒字化)つまり「利益が出た」だけでは満足しないのです。
「利益が出た」と「利益が増えた」の間には、天と地ほどの差があります。資本主義経済、資本主義的企業間競争は、どれほど困難であろうと「利益の増加」を求めてくるのです。
したがって「経営計画の作成」にあたっては、「利益の増加」の可能性の追求を条件としなくてはなりません。さらに社会のために、コストの増加も併せて追及しなくてはなりません。二重三重の困難に挑戦しなくてはならない訳です。
これこそ、Up Down方式経営分析が、経営に求めるもので、黒字化以上の「困難」にあえて挑戦しようとする覚悟を「経営の評価の起点」にするものであります。
UpDown方式経営分析

Excel仕様の”決算評価書”については
(有)鈴木会計事務所へお問い合わせを

↓専用ページへ移動します↓
| 事務所名 | 有限会社 鈴木会計事務所 鈴木信行税理士事務所 |
| 所長名 | 税理士 鈴木 信行 |
| 所在地 | 福島県福島市飯坂町平野字大前田1-71 |
| 電話番号 | 024-542-6064 |
| FAX番号 | 024-542-6071 |
| 業務内容 | ・Up Down方式経営分析 ・決算評価書の提供 ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 |