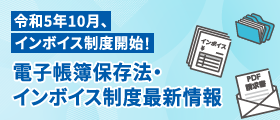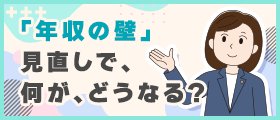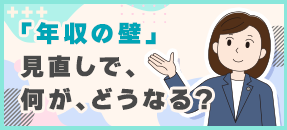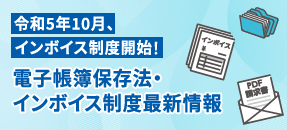知識と知恵は企業の力
ご挨拶
ほぼ10年をかけて決算書の見方さらには経営に於ける決算書の利用について考察を重ねてきました。
途中「決算書を超越しよう」(Up Down方式経営分析)という題名でワークブック的な書を自費出版いたしました。
それは現在の到達点へのキッカケとなった考え方を綴ったものでした。
紆余曲折を経て現在に至っていますが、当初の考え方はブレずに踏襲しております。
その到達点は四つになります。
一つ目は、「決算評価書」作成の提案です。その手法はUp Down方式経営分析(二項目増減分析)と言えるものです。動線分析と点数化が大きな特徴です。その考え方は様々に視点を変えながら、繰り返し説明をしております。
二つ目は、円の理(この概念図は別途表示してあります)に基づいて決算書の主要項目(勘定科目など)を円周として描きそれぞれの項目をUpとDownで二色で彩色したものです。その図を見ながら、視覚的に、相互関係、二項目の因果関係を見いだし、問題意識化すると言うものです。
三つめは既存の決算書の彩色化の提案です。決算書そのものの彩色化提案はアイデアとしては前代未聞のことでもあります。決算書そのものの彩色化はすべての項目の「増減という属性」を見える化したものです。経営分析資料として決算書とは別途作成しても良いでしょう。その効用は表示方法の単なる工夫を超えるものと期待されます。Excelを使用して誰にでも作成可能です。アップしてありますのでご覧ください。
四つ目は、経営判断において課題の種類に関わらず常に「二項目同時考察」という態度を取ろうという提案です。比喩的に「新二刀流経営」と名付けております。
これらの提案は、経営の激しい変動についていける決算書と経営分析や経営評価を目指したものです。「過去のモノ」という評価を「今使えるモノ」という評価へ大きく変身したと思っています。
以上の提案は、会計や決算書の経営への利用を広げ、会計や決算書が経営を良くするための無くてはならないものになってきたと考えています。そもそも決算書無しでは経営は成り立たないわけですから。
少子化という経済の根本的困難を目の前にして、企業の特に大多数の中小企業の困難突破の一助になればと思っております。
なお、新視点からの新しい論理(小論)を随所に掲載しておりますので経営分析を研究中の方、経営分析に深くご興味の方はご高覧、ご批判いただければ幸いです。
福島市 (有)鈴木会計事務所
四つのイノベーション
★Up Down方式経営分析決算評価書
★Up Down方式問題発見のための決算項目相関図
★Up Down方式二色彩色決算書
★Up Down方式経営(新二刀流経営)
専用ホームページで随所に新経営分析理論掲載



Up Down方式経営分析・決算評価書
新経営分析のどこが既存の経営分析と違うのか?
(その一)
経営分析指標は中小同族会社に不評!?
会社の大多数(80%を超す)を占める中小同族会社にとって「経営指標による経営分析」あるいは「経営指標そのもの」は極めて不評です。
そのことを指摘している「経営書」は皆無に近いでしょう。只々「決算書の重要性」「経営分析法の必要性と詳細な説明」を強調するのみです。
不評の一つの原因は、中小同族企業の性質にあると考えられます。
戦後、自主申告制度の普及とともに青色申告運動があり、個人事業者は複式簿記による自主申告をするようになりました。その過程で「法人成り」ということで個人ではなく会社組織での経営が普及していったのです。
ここに登場したのが、社長給料や家族の役員報酬です。これらは同族で決定できるため営業利益は意のままと言っても良いでしょう。
また、関連同族会社の設立を含め所得の分散も自由となりました。
これらは当然、税法の規制(損金不算入)の対象ともなったのですが、その自由性に変わりはありません。建設業の工事原価の中での請負金額の分散などは容易にでき、その外注費により粗利益は意のままになったと言えましょう。
「経営分析」と言う視点では、今述べ2点だけでも、粗利益率や営業利益率、工事原価率や販売費及び一般管理費率、労働分配率など「重要な経営指標」が、真の経営の姿とは乖離し、無益な分析となってしまいます。
大企業では有効な指標も、中小同族会社では意味をなさない指標となってしまうのです。
成長中の優良中小同族企業が、巨額の役員同族報酬を支払って、利益はわずかということもあり得るのです。
逆もあります。役員報酬をほとんど取らず、黒字計上としたらどうでしょう。
企業の栄枯盛衰評価や成長把握には、この矛盾をぬぐいさる「新経営分析」が必要です。
もう一つの原因は、損益計算書分析は一年間の分析で、貸借対照表分析は、会社の誕生から今までの生涯分析だと言う明確な視点の不在です。
Up Down 経営分析と「決算評価書」はこのことを強く意識し登場したものです。経営指標のあいまいさを指摘したのです。
「コストと利益」の同時増加を「成長」とするという新視点・定義は、真の経営の状態、経営の栄枯盛衰の把握に成功したと考えています。また自己資本比率に変えてまずは、総資産と純資産の増減の生い立ちまでを考える「キャッシュと純資産」の同時増加を「成長」とする視点を加えたのです。
(その二)
中小同族企業にとっての未来予想の精度を高めた
『利益』は会社の大きさに関わらず「期末決算書」を見なければ分かりません。
『売上』は会社が小規模であればあるほど「当初予想」が頻繁に外れます。
「費用」は小規模企業にとっては「固定費」ではなく頻繁に発生する臨時費用などのため「変動費」と言って良いくらいです。
予想の困難が経営計画作成の意欲をそぎます。
そこで新経営分析は「会社の真の動向」を瞬時に表示することによって、今までと異次元の予想を可能にし、また瞬時の予想修正に役立ちます。
月次決算、年次決算から経営の「今の動向」を瞬時に察知し、予想の変更を可能にするのです。
(その三)
成長とは?に明確な定義と視点を与えた
世にある「成長戦略」に関する記述のほとんどが売上とか利益とか、ほとんど「単一項目の成長」として、それぞれに考察とされています。
今回経営分析、経営評価の分野ですが、Up Down方式経営分析において、二項目同時考察が新しい視点として登場しました。この新しい視点は、二項目の関連性における矛盾や困難や相乗効果性が否応なく考察されることになります。
この視点を登場させることによって、既存の「成長戦略」がより豊かになると考えられます。
個別企業の「経営目標」策定の際の二項目同時増加については、Up Down方式経営分析専用ホームページで紹介しております。
あわせて、ご覧ください。
(その四)
「経営計画と実績の比較」と「Up Down方式経営分析」はともに自己努力と社会的条件の混在した中での経営の現状を示してくれます。
経営の繁栄は自己努力と社会的条件(景気などの条件)によって決まります。
経営のUp Down方式経営分析、栄枯盛衰(成長)分析は、その両方の要因を含めた評価書としての決算評価書として一応の完成を見ました。
一方、「経営計画」と「経営結果」との差額も、自己努力の結果と同時に社会の景気の現状も知らせてくれます。つまり、経営計画と実績の差額も、自己努力と社会の景気の変動と言う混在した二つの要因に影響を受けます。
結論を言います。具体的な数値目標との比較という点で経営計画は優れており、会社の大多数派である中小企業にとって手軽で「体温計的」であるという点で決算評価書は優れています。経営計画のない中小企業が多数を占めているのが現状です。
その「利便性の違い」から併用するのが、ベターではないかと考えます。

決算書とはなにものなのか?
決算書のうち損益計算書(P/L)は会社の一年間の利益(儲け)を計算する場であり、報告の場であります。黒字だったか赤字だったかを知る”唯一の場”です。
次に貸借対照表(B/S)は会社の設立から今までの総括の場、結果報告の場であります。例えば第60期の貸借対照表は60年間の結果生じた現在の姿を報告していることになります。キャッシュの残は開業から今までの入金から出金を差し引いた残高です。一夜(一年)で得たものではありません。㊟多くの人が指摘している。
決算書のP/Lで今を見、B/Sで歴史を見ていると言って良いでしょう。
決算書とは財務とは言え「企業を知る」ためには「無くてはならないも」のなのです。
Up Down方式「決算評価書」はなぜ会社のコンディションを測る道具(会社の体温計)となったのか?
その重要な「決算書」をどんな決算書解説より「早く読み取る方法」を提示したからでしょう。
決算評価書はどんな考え方から出来ているでしょう。
最初に書いたように、自社や他社の現在と過去を知るには、決算書を見る以外に方法はありません。
決算書の本質は、「利益の計算機・利益の唯一の報告書」かつ「会社の歴史の報告書」だからです。
そして、会社の「最近の動向」を知る方法は「前の決算書」と「直近の決算書」を比較する以外に方法はありません。
それは、「決算書内から抽出した二つの項目」が前年と比較して「増加と増加(ダブル増加)」であれば「成長!」「増加と減少のチグハグ状態であれば「停滞!」「減少と減少(ダブル減少)」であれば「衰退!」という「定義」です。
なぜそう言えるのか?
経済や経営に存在する二つのカテゴリーはお互いに原因であり結果なのです。例えば売上が増えれば利益が増え、利益が増えれば売上が増える、という関係性です。「どちらかが増えれば片方が増える」という単純な一方通行とは言えないのです。両方増えてこそ成長があると言えます。
我々はどうしても二項目を原因と結果に分け原因改善に目標に絞りたがります。売上さえ増えれば、あるいは利益さえ出ればという様に。
「二項目の共存性(持ちつ持たれず)」という考えには及びませんでした。この「二項目の共存性」という考え方から「Up Down方式経営分析」が登場しました。「決算評価書」はその結晶です。出来上がってしまえば、至って単純で簡単なものとなりました。
「あなたの会社は今成長してますか?景気はどうですか?」と聞かれた時、即座にお答えできていたでしょうか?
★売上は増えているけど利益は減る一方
★コストダウンなどで、利益は出しているけど、売上は激減しているが?
★コストを掛け、売上も徐々に増えているけど、利益は増えないけど?
Up Down方式新経営分析(決算書二項目増減分析)の「決算評価書」は、初めて明確な答えを出しました。
上記の★のいずれにも「停滞」という判断を下したのです。
また決算評価書では、会社の栄枯盛衰の今を「図式(四つの動線)と点数」という大胆な方法で表現しております。さらに点数化までしました。
上場会社から中小同族会社まで、公益法人なども含めて、会社のコンディション「成長か衰退か」が一目で分かるようになったのです。
しかも、数字や率ではない「増減表現」にこそ、会社の核心を突いた「最重要秘密」が存在すると言っても良いでしょう。
二項目増減分析こそが、会社の「数字に隠れた実態」を真に表現していると言えるのです。
逆に二項目増減表現の前では、「数字や率」はまるで経営の「核心部分を隠すベール」のようにさえ見えてくるのです。
その手軽さと、企業のコンディションを真に知ることが出来るため、決算評価書は「会社の体温計」と言っても良いものになったのです。
さらに決算書は実は「他社」の景気をも表現しているのです。我社の費用は他社の売上です。コストダウンは他者の不景気を意味します。ここに大きなヒントがあります。大きな会社がすべて「コストダウン・費用削減・賃金カット」をしているとすれば、日本の景気は全体としては「不景気」なわけです。
決算評価書が一会社の分析に留まっていないことを意味します。このことは別のところで再指摘しています。
新‼【Up Down 方式決算書】
著作 (有)鈴木会計事務所
この二色彩色の新らしい決算書は既存の決算書そのものを変えることなく増減だけを意味する二色で彩色したものです。
その完成したものは、項目や数字の意味と同時に「増減」を我々に知らせてくれます。
有りそうで無かったものです。
その効用は計り知れないものです。「そのままで、色だけで」経営の変動を感じさせてくれます。
見本をご覧ください。
説明すらいらないものです。
新二刀流経営
Up Down経営分析法は新二刀流経営を暗示したと考えています。
現在では、二刀流経営は別の意味で採用されています。例えば二つの業種を同時に行うということや、一人の人間が個人経営と会社経営という二つの形態で同時に行うということです。そして同時に行うことにより経営の繁栄成長のための相乗効果を狙うというものです。
ここでいう「新二刀流経営」はイメージ図にあるように決算書内の経営分析に使った二つの重要項目や基本項目を経営の際、同時に「目標化」「実行」「検討」「チェック」「評価」することを言います。
売上と利益を因果関係の中でより深く考察し、また時には相矛盾する二項目の同時増加を図るというようなことです。
「人件費と売上」「人件費と営業利益」など多くの問題を二項目考察で行くことが出来ます。

黒字企業の「数や割合」で
世の中の景気を計ることが出来るのか?
おしまいに
あらためて、関係方面の皆さまへ
「Up Down方式による三つのイノベーション」をぜひご覧ください。
棒グラフは、誰が見ても分かるように、増減二色彩色付き決算書は誰が見ても企業の変動を感知できます。
「決算書アレルギー」も無くなり決算書が身近になることでしょう。
決算書の彩色化が容易に出来るのは「会計ソフトの作成にあたっているソフト会社、AI開発にあたっている会社、場合によっては、コピー関係の複合機のソフト改良にあたっている会社、などなど」沢山の関係方面があると思います。
そのうえで、さらに「Up Down方式経営分析や決算評価書の作成」に興味がある方は取り組んでいただきたいと思います。
また「新二刀流経営」というものも熟成していただければと思います。
世の中「一項目での議論」が多すぎると思います。それは他を論破するのには都合の良いが、どこか生産性に欠けるものと思われます。自分に都合のいい主張は大体「一点主義」の主張です。この車は早い!この保険は安い!決算書が読めない経営者はダメだ!・・・・・などなど。
どうかUp Down方式の二項目主義の世界をご体験くださるようお勧めいたします。決算書や経営が立体的に見えてきます。新しい視点での説明も可能になるでしょう。
お知らせ
Up Down方式経営分析の結晶”決算評価書”のエクセル版(見本)を詳しく知りたいと思われる方
Up Down方式経営分析のノーハウを詳しく知りたい方は
お問い合わせフォームその他で、(有)鈴木会計事務所にお問い合わせください
UpDown方式経営分析


↓専用ページへ移動します↓
| 事務所名 | 有限会社 鈴木会計事務所 鈴木信行税理士事務所 |
| 所長名 | 税理士 鈴木 信行 |
| 所在地 | 福島県福島市飯坂町平野字大前田1-71 |
| 電話番号 | 024-542-6064 |
| FAX番号 | 024-542-6071 |
| 業務内容 | ・Up Down方式経営分析 ・決算評価書の提供 ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 |