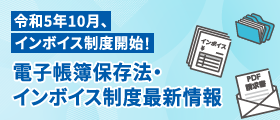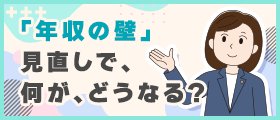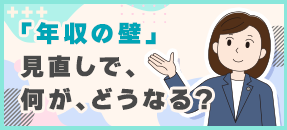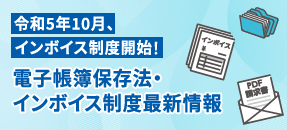令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
お知らせ
税務ニュース
1月 職員からのお知らせ

担当者:塩見
*医療費控除について*
確定申告の時期になりました。医療費控除についてご案内します。
医療費控除は申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和7年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
(令和7年中に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。医療費の領収書が多い場合は、国税庁のホームページより医療費集計フォームをダウンロードし利用することができますのでご確認ください。
また、医療費の領収書は自宅で5年間保管する必要がありますので大切の保管してください。
セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。選択適用となります。また、修正申告又は更正の請求において、選択を変更することはできませんので注意してください。
今年の確定申告についても、早めに準備をして申告期限までに提出できるようにしてきましょう。

担当者:角田
*確定申告寄付金控除(寄付金控除に関する証明書)について*
寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」等の添付が必要です。
令和3年分以後の確定申告においては、特定寄附金の受領者が地方団体である場合(特定寄附がふるさと納税である場合)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
(例:さとふる、ふるなび他27件)
国税庁長官が指定した特定事業者一覧が国税庁のホームページに記載されていますのでご確認ください。

担当者:山野井
*防衛特別法人税の創設*
国税庁HP参考
新年、明けましておめでとうございます。
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。
これに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となります。
防衛強化税率は、急速に変化するわが国の安全保障環境に対応し、防衛費を安定的に確保する目的で新設される税制です。この制度は2026年4月以降に始まる事業年度から適用され、基準法人税額に対して新たに4%の付加課税が行われます。
ただし、基準法人税額が500万円以下の中小企業は課税対象外となり、対象となるのは基準法人税額が500万円を超える企業ですので、法人税額が一定水準を超える企業を対象としています。
中小企業の多くは課税対象外になりそうですが、法人税額が500万円以下の企業にとって直接的な金銭負担はないとしても、申告義務があること、そして税務の複雑さが増すことは間違いありません。企業は税負担が増大することを見込んだ長期的な経営戦略を立てることが重要ですし、施行開始に向けて、経理・税務担当者は最新の情報を確認し、準備を進めていくことが求められます。

TKCコンテンツ
関与先企業の繁栄は私たちの喜びです。
当事務所では適正申告を目指して記帳指導、業務改善指導等を実践したノウハウを生かし、申告是認となることを目指して、ご支援を行っております。
お気軽にご相談ください。
事務所概要
| 事務所名 | 平間武義税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 平間 武義 |
| 所在地 | 福島県相馬市馬場野字雨田99-1 |
| 電話番号 | 0244-36-1215 |
| FAX番号 | 0244-36-1217 |
| 業務内容 | ・法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成 ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・試算表、経営分析表の作成 ・総勘定元帳の記帳代行 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・各種書類の作成 |
| 東北税理士会所属 |