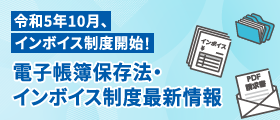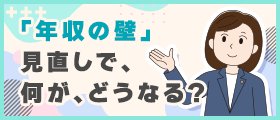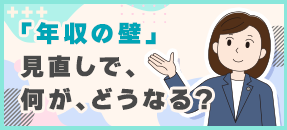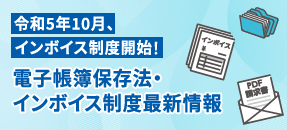北島会計グループは、よりよい社会の 実現に向けて国際社会が2030年までに達成を目指す持続可能な開発目標(SDGs)に対し、次の活動を通じて『共生ビジョン』の世界実現に貢献していきます。
→詳しくはこちらからご確認ください。
北島会計グループは、練馬区の石神井町、石神井台、高野台、上石神井、下石神井、大泉学園町、東大泉、西大泉、南大泉をはじめ関東全域で税理士業務、社労士業務、行政書士業務をさせていただいております。相続税、法人税、所得税等税務や会計の事に限らず、経営全般のご相談もお受けいたします。

顧問契約のお客様の途中解約が45年間で1件もないことが、お客様からの評価です。

弁護士、司法書士、行政書士、保険会社、銀行等との提携により全ての手続を行えます。

徹底したコスト管理で練馬一のコストパフォーマンスを実現。是非当事務所のサービスを吟味ください。

貴社専任のスタッフが定期的・継続的に訪問することでお客様との強い信頼関係を築けます。
そして、会社経営に関するあらゆるお悩みにも専門チームにて迅速にお応えします!
例)事業計画・会計税務・人事労務・法務・IT・収益拡大・コスト改善・事業承継・相続・新規顧客開拓・国際税務まで

税務調査も万全の備えで安心!
(経験豊富な3名の国税OBと実績豊富なスタッフが連携)

定期セミナーで人脈&ビジネスチャンスをGetできます!!

「親切・丁寧・迅速・正確・しかもリーズナブル」で地元密着型のオンリーワン事務所を目指しています。

資産税が人気です。相続の生前対策、資産管理・運用など何でもご相談ください。
事務所概要
| 事務所名 | 税理士法人北島綜合会計事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 北島 弘太郎 |
| 所在地 | 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-13-17 龍英ビル3F |
| 電話番号 | 03-3995-3661 |
| FAX番号 | 03-3995-4568 |
| 業務内容 | 経営相談に関する業務 |